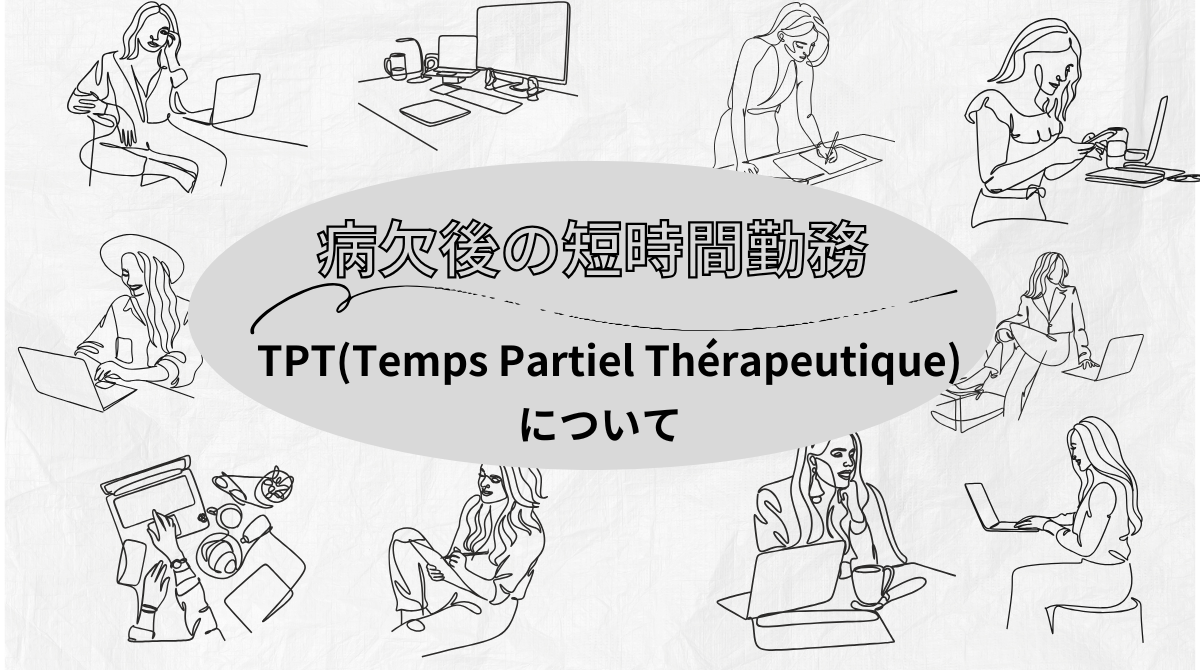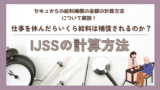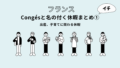健康上の理由で契約上の勤務時間を遂行することが難しい…
長期の病気療養後に少しずつ業務へと復帰したい…
そんな時に使えるのがTPT(Temps Partiel Thérapeutique)もしくはMTT(Mi-Temps Thérapeutique)と呼ばれる短時間勤務の制度です。
短時間勤務によって生じる給料の減額はCPAM(健康保険事務所)が補います。
事故や病気で職場を長期に離れることになった場合、無理せずに少しづつ業務へと戻ることのできるこの制度について記事内で詳しく解説していきます。
TPTの仕組みについて
TPTとは病気や事故の後遺症等の健康上の理由で業務を100%遂行することができない場合に、かかりつけ医、労働医、会社のRHとの面談を経て労働時間を一定の期間減らす制度のことです。
例えば週35時間勤務の人が50%のTPTの診断書を提出し会社側が了承すると、労働時間は週17,5時間となり、その労働時間に応じた給料を受け取ることになります。
会社側は毎月CPAM(健康保険事務所)に社員が実際に受け取ったその月の給料とTPTによる減額分を証明する書類を送り、後日CPAMが給料の減額分を社員に直接補償します。
TPTが利用できる期間は通常は合計で1年です。
一方で、会社側がTPTを拒否することもできます。
その場合、労働医が当事者にInaptitude(不適合)の診断を下し、ポスト替えもしくは解雇手続きにはいることになります。
TPT制度の目的
TPTは実際の労働現場でよく使われる制度です。
病気治療で1ヶ月、3ヶ月と休んでいた人が翌日から職場にフルタイムで復帰するのは現実的にはなかなか難しいものがあります。職場復帰の疲労とストレスが新しい病欠を招くことになるかもしれません。
TPTの制度の利用は、社員にとっては収入の心配をすることなく、段階的に職場への復帰を果たすことができるという利点があります。また、CPAMの側は病気休養で支払われるIJSS(セキュから支払われる手当金)の削減に、会社側は社員が職場から長期間離脱することを避けることができます。
2020年以前は病気療養→TPTという流れが必須でしたが、2020年以降は病気療養の前段階がなくても、かかりつけ医は直接にTPTの診断書をだせるようになりました。
短時間勤務から補償を受け取るまでの流れ
では詳しい流れについて以下で見ていきましょう。
①かかりつけ医の診断
かかりつけ医が、貴方が100%仕事復帰ができる状態かどうかを診断します。限定的に仕事へ復帰できると診断された場合、20%から90%の間で職場復帰の割合を診断書に記入します。
②労働医との面談
かかりつけ医の診断書をCPAMと会社のRHに送付し、後日会社側から労働医との面談日を指定されます。
労働医はまず貴方が元のポストに戻ることができるかどうかを判断し、Apte(相応)もしくは限定的にApteと認められた際には、かかりつけ医の場合と同様に職場復帰の割合や条件を決めます。
また、労働医は職場復帰に際しての提言も行います。
例えば5キロ以上の荷物を持たせてはならない、30分交代で座ったり立ったりと姿勢を変えること、車の運転をさせてはならない等々、雇用主側と職場環境に関する意見交換を行います。
③会社のRHもしくは雇用主との面談
かかりつけ医と労働医の診断書を基に会社側がTPTが可能かどうか判断します。(場合によっては②と③が前後する)大抵の場合、会社側はTPTを受け入れますが、会社側が拒否することもあります。
①会社側がTPTを受け入れる
会社側が了承した場合、具体的な労働時間と労働日の割り当てについて話合いが行われます。TPTの割合に適した新しいAvenant(契約の更新)が結ばれる場合もあります。
②会社側がTPTを拒否する
会社側は正当な理由があればTPTを拒否することができます。
会社側が拒否した場合、以下のような解決策があります
- かかりつけ医が病欠証明書(Arrêt de travail)を出して病欠になる
- TPTが可能なポストに一時的に配置替えされる
- 労働医が2が不可能だと判断した場合、今のポストへのInapte(不適応)を宣言され、会社側から別のポストを提案される。その提案を従業員側が受け入れなかった場合、解雇手続きにはいる。(Licenciement pour inaptitude/従業員の健康状態を理由にした解雇)
会社側が拒否する場合とはどんな状況でしょうか?職種によってはTPTを実行すること、労働医の提言を受け入れることが難しい場合があります。
例えば70%のTPTの診断が下された場合、会社側は残りの30%を補うためにCDDを雇うことになります。小売りや飲食業の場合、週末だけバイトをしたい学生さんがいるので週10時間のCDD契約を結ぶことは難しくないでしょう。
しかし、配送業や医療関係など、専門性が高まると、週10時間のCDDという条件に応募してくる人はほぼいません。
また、労働医から30分以上の立ち仕事は禁止する、と提言された場合、レストランやホテル業でその条件を受け入れるのは大変に難しいでしょう。
こうした「拒否するに足る正当な理由」を会社側が提示できる場合、会社側はTPTの受け入れを拒むことができます。
④勤務時間変更による給料の減額
元々フルタイム(週35時間、月151,67時間)で働いていた人が病気療養の後50%の割合で職場に戻る場合、週17,5時間勤務となり、会社側はその勤務時間に応じた給料を支払います。
例えば…
週35時間(月151,67時間)で2000€の収入を得ていた人が50%のTPTを理由に週17,5時間(月75,83時間)勤務に従事する場合、会社から振り込まれる給料は、2000 / 151,67 x 75,83 = 999,93€となる。
⑤セキュから損失分の補償
月の終わりに、会社側はTPTにより失われた給料分の証明(Attestation de salaire)をCPAMに提出します。
CPAMは会社側の申告に基づいて、減額分相当を手当金(IJSS)として従業員に支払います。
病気で会社を休む際、通常は3日の待期期間ののち、4日目からIJSSが支払われます。
また、手当金は過去3ヶ月の平均給料の50%です。
一方で、TPTの場合は待期期間や支払いの上限はありません。減額分=手当金(IJSS)となります。よって、上記の2000€の基本給で50%のTPTの場合、会社側から999,93€を受け取り、CPAMから2000 – 999,93 = 1000,07€が後日振り込まれます。
⑥短期時間勤務の上限
TPTの期間には上限があり、通常は1年です。ただし、TPTの原因となる症状が労災(Accident du travail)や職業上の疾病(Maladie professionnel)によるものかどうか、TPTの期間に違う病気で休んでいた等々、状況によってTPTの期間が延長になることがあります。
TPTの期間が終了した後、従業員はTPT前の契約時間に戻ります。
まとめ
TPTもしくはMTTと呼ばれる短時間勤務の仕組みについてみてきました。
ケガや病気からは快復したけど、100%の状態で現場に戻れるか心配だ…仕事はできるけど特定の動作を繰り返すと痛みが増す…といった場合、無理をせずにかかりつけ医に相談しましょう。
TPT終了後、テレワークが可能な職場であれば、症状に応じて労働医からテレワークの日を増やすように職場に働きかけてもらうことができます。(Télétravail sur prescription médicaleと呼びます)
雇用主側に履行の義務はないので、あくまで労働医からの提言にすぎないのですが、職場に相談して理解を得ることができれば、テレワークの日を例えば1日から2日、2日から3日へと増やすことができます。
かかりつけ医、労働医、会社のRHもしくは雇用主と相談して、自分の体の状態に相応しい形で職場への復帰ができることが一番ですね。